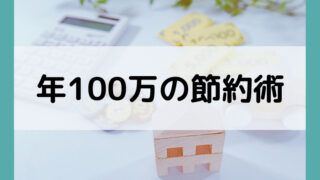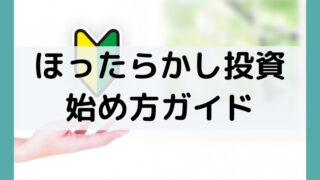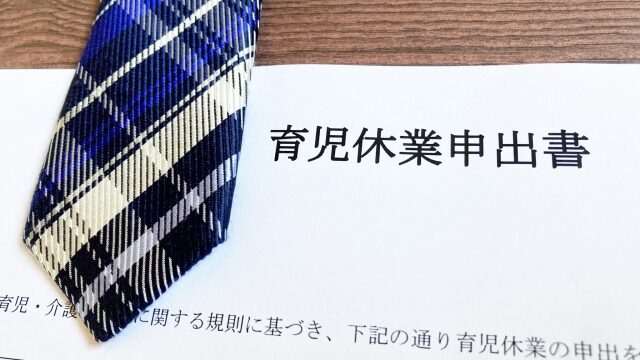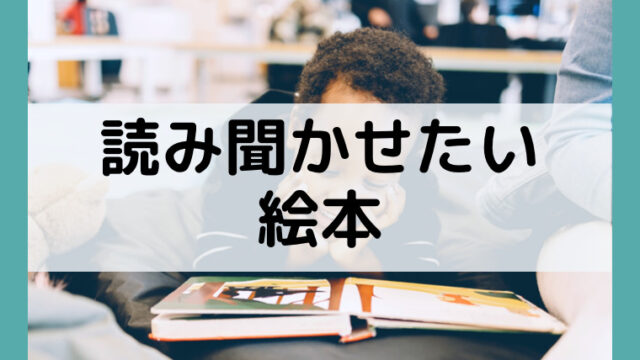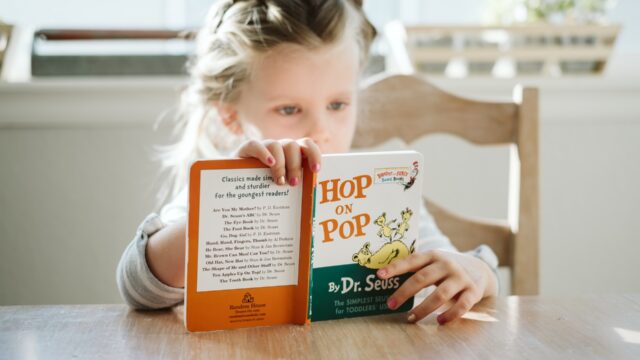2025年12月下旬に、第二子となる長男が生まれ、これに合わせて、1年間の育児休業を取得することにしました。
私は、
・地方公務員の一般事務職
・入庁10年目(当時)
・第一子が生まれた時は1ヶ月間取得
です。
職場では、男性職員が短期育休(1週間〜1ヶ月程度)を取得するケースは増えている実感があります。
しかし、3ヶ月以上の育休を取得する男性職員はまだまだ少ない印象です。
同じ職場の別の同僚(男性)は、3ヶ月の育休を希望したところ、上司から「職場が回らないから、1ヶ月にしてくれ」と言われ、飲まざるを得なかったと聞き、驚愕しました。
1年間の育休取得を決めた理由を紹介し、育休取得について考えているパパの参考になればと思います。
1年間の育休取得を決めた理由
私が育休の期間を1年にした理由は、以下のとおりです。
①1ヶ月の育休では短いと感じた
②我が子の成長をじっくり味わいたい
③妻が大変なのは産褥期だけじゃない
④子ども、家族と旅行など色んな経験をしたい
⑤一生に一回の機会、取らないと後悔する
⑥取ってみて、はじめて見える景色がある
正直なところ、「本当に1年間取得できるのか」、不安と葛藤はありましたが、職場も好意的で助かりました。
①1ヶ月の育休では短いと感じた
一人目の長女が生まれた時、1ヶ月間の育休を取得しましたが、その時の率直な感想が「短い」でした。
一人目の時、妻が産後1ヶ月間里帰りしており、その後アパートに戻ってくる時期に合わせて1ヶ月の育休を取得したので、新生児期の育児はほとんど関わることができなかったことも、悔いが残っていました。
②我が子の成長をじっくり味わいたい
③妻が大変なのは産褥期だけじゃない
理由①にも通じますが、育児にじっくりと向き合うには、1年間程度の長期スパンが必要だと考えました。
また1人目の子育てを通じて、0歳→1歳に至る過程は、寝返りやハイハイ、離乳食など様々な行動変容があり、大変なのは産後すぐ(産褥期)だけじゃないと実感したので、その時期も妻を支えたいと考えました。
加えて、3歳になる長女もいるので、上の子を見ながら、赤ちゃんのお世話から家事を妻一人に任せるのは負担が大きすぎると判断しました。
娘が4月から幼稚園に入園する予定だったので、娘と家で一緒に過ごす時間も確保したいと思いました。
④子ども、家族と旅行など色んな経験をしたい
⑤一生に一回の機会、取らないと後悔する
子どもと関わるまとまった期間を確保する上で、育休はまたとないチャンスだと考えました。
私たち夫婦は旅行が好きなので、この機会に子連れ旅に出かけたいという思いもあります。
また、それ以外にも様々な活動や人との出会いを通じて、今までとは異なる新しい価値観に出会えるかもしれないとも考えてました。
旅の記録は今後、このブログでもご紹介したいと思います。
⑥取ってみて、はじめて見える景色がある
一旦、育休で仕事と距離を置くことで、家族と向き合い、色んな経験をしてみて、初めて気づくことがあるかもしれないと考えました。
また、私が取得することで、今後、育休を取りたい後輩の気持ちを理解し、サポートできるようになるかもしれないとも思っています。
女性が育休制度を切り開いたように、男性の育休も過渡期です。
自分の選択が、組織、ひいては社会の考え方を変えるきっかけになると信じています。
1年間の育休に踏み切れた要因
とはいえ、お金の面で心配があると思い切った選択はできません。
節約や投資で家計を強化していたことが、1年間の育休に踏み切れた大きな要因の1つです。
普段から固定費の見直しや、インデックス投資、高配当投資を実践していたので、育休を取得しても収支の見通しを立てることができたのは本当に大きいと考えています。
お金は人生の選択肢を広げてくれると実感しました。
育休手当金と生活費の試算
具体的に試算した内容をご紹介します。
我が家の年間支出額は、ざっくりと400万円です。
一方、収入に関して、私の育休手当金は200万円、妻は無職のため育休手当金は0円。
私の貯金(生活防衛資金)が90万円程度。
不足する110万円を、投資信託を売却して捻出する予定です。
実際には旅行の費用もあると思うので、もう少し投資信託を切り崩すことになると思います。
関連する記事
我が家が実践する節約や投資については、以下のリンクからご覧ください。